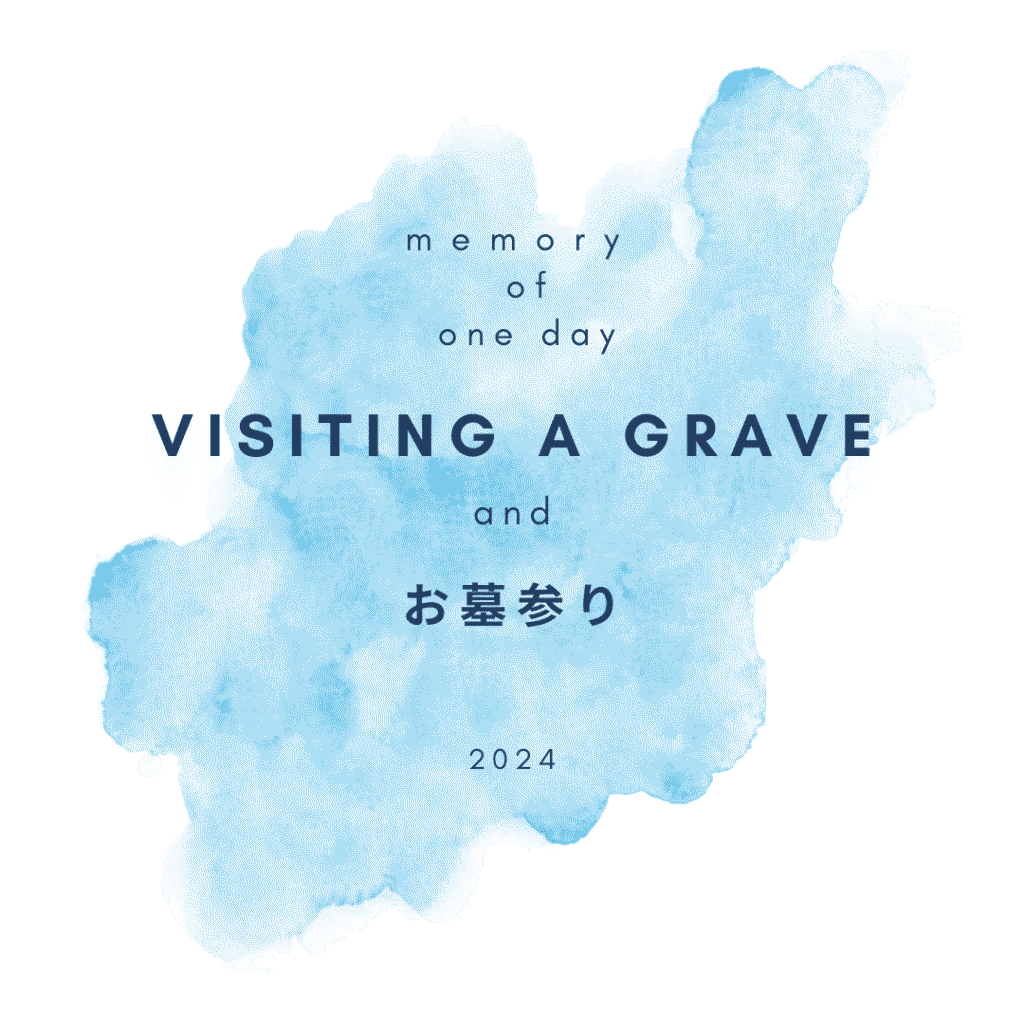
毎年恒例『8月の大イベント』
それが…家族揃っていく「お墓参り」です✨
父が亡くなるず〜っと前からおじいちゃんやおばあちゃんのお墓参りは必ず行くことになっていました。なので、物心がついた時から「8月は家族でお墓参りをする」「お墓参りへ行く」ということが当たり前の『藤井家の夏☀️』を今回はお届けしたいと思います。
※「お墓参り」の考え方や思考は人によって違うものだと思っています。
なので〜アコさんの見解というよりは「藤井家の見解」はごくごく一家庭のことであって誰にでも当てはまることではございません。
その点をご理解した上で読みすすめていただきたいと思います。
よその家がどんな感じで「お墓参り」をしているのか!?
- お墓参りに何をやっていいのか分からない方
- お墓参りにどんなことをしているのか知りたい方
- お墓参りの「決まりごと(基本)」を知りたい方
今年も家族3人で!!
とある8月某日。1日で3カ所の霊園をめぐる『藤井家のお墓参り』
今年の天気は「雨が降りそうだったけど…」半日”くもり☁️”がつづき〜
何とかお墓参りを無事おえることができました✨
これもきっと…
『天国にいる父がお墓参りの時間帯だけ雨をずらして”くもり☁️”にしてくれてる?のかな?!』と思うほど亡くなってから24年ほどたつけど…雨が降ってたのって…
覚えているかぎりでは2〜3回あるかないかぐらいだったと思います。
(→それぐらい藤井家の父は空の方で「天候を左右できる役職?!」を担っています)
「お墓参りのルーティーン」
49歳のアコさんが少なくても〜
ここ40年は続けている
「お墓参り」の1日の流れです
| 7:00▶️ | 車で家を出る |
| 7:20▶️ | ばらと霊園に到着(父のお墓があります) |
| 7:33〜8:15▶️ | 父のお墓の前で「お供物兼朝ご飯を食べる」 |
| 8:59〜9:28▶️ | 平岸霊園に到着(母方の父母、親戚一同のお墓) |
| 10:37〜10:51▶️ | 岩見沢サービスエリア(トイレ/ソフトクリーム) |
| 11:15〜13:23▶️ | ピパの湯 ゆーりん館(お昼ご飯/温泉に入って休憩) |
| 13:39〜14:18▶️ | 美唄 沼貝寺(父方の父母、親戚のお墓) |
| 14:20〜▶️ | 美唄→札幌へ一般道から一旦自宅へ |
| 17:00〜▶️ | 夜ご飯は外食(とんでんへ) |
ざっとこんなスケジュールで毎年「お墓参り」へ行きます。他の家のことが分からないので何とも言えませんが…
藤井家では父が亡くなる前から行き先はほとんど変わらず、「ばらと霊園」「平岸霊園」「美唄の沼貝寺」へ行くことがお決まりのことになっています。
小さい頃から変わらないことなので、他の家と違うところ…と言えば『父のお墓の前で供養した後に、お供物をその場で食べる』っていう行為がもしかしたら〜めずらしいことかもしれません。
父のお墓の前で「家族みんなでご飯を食べる」慣習がある!
小さい頃からずっ〜と「お墓参り」といえば…
おじいちゃん、おばあちゃんのお墓の前で供養した後に、
「お供えしたものをみんなで美味しくいただくこと」が当たり前。
ここ20年くらいは父のお墓の前で折り畳みの小さい椅子を3人分並べて父のお墓を見ながらお供物(食べ物や果物、飲み物)を家族でいただきます。
あと私は母と兄に聞こえるように…
『最近、うちの家族はコミュニケーションがとれてなくて、バラバラなんだよね!どう思う?父さん!!空から見えてますかぁ〜?』と、
お供物のお稲荷さんとザンギを食べながら父へ報告してきました。
(→当然、母と兄にも聞こえているのに「何を言ってんの?」と聞こえないフリ&笑って誤魔化してたけど…言いたいことは毎回全部、父のお墓の前で言ってきています (´∀`*)/)
↓お墓の前でこんな感じで家族みんなで「お供物」をいただいております。
お墓を見ながらなので「亡くなった父とご飯を食べているような、家族が4人揃った嬉しさもありつつ…」で食べ物を食べながら泣きそうになるときもあります


↑昔は重箱?!みたいなお重に買ってきた食べ物や果物を入れて持ってきてたけど…
ここ15年くらいは買ってきた食べ物をそのまま「お供物として」お参りをする時まで供えて、お参り後は下げて『家族でおいしくいただくこと』が慣習に✨
「父さんの好きなものって…この中にある?!」
「お墓参りのマナー」とか詳しいことは分からないまま…
小さい頃からやってきた『ご先祖様のお墓の前で家族や親戚一同で供養した後にお供物をおいしくいただく行為』は心がポッとあったかい気持ちになります。
そして毎回『亡くなった父やおじいちゃん、おばあちゃんに会いたくなる気持ち』になって帰ってきます。
| 小さい頃はお墓の前でみんなで亡くなった人の思い出話や人柄などを話しながらワイワイしていて「お供物をおいしくいただくこと」がすごく不思議だった。 お墓の前なのに大人たちがみんなで笑顔になったり思い出して泣いてたり〜それぞれの喜怒哀楽する姿を生で見ていて… 『亡くなったおじいちゃんやおばあちゃんも笑ったり泣いたりしてそう…✨』と子供ながらに何か「良いことをしているような感覚✨」があったことを思い出しました。 |
お墓参りの「決まりごと(マナー)」ってあるの?!
一般的な〜お墓参りの「決まりごと(基本)」をアコさんなりに調べてみました!ぜひ参考にしてみてください。
「お墓参り」をする行為について…
- 「お墓参り」のやり方に『こうでなければいけない』ということはないそうです。
- 家族や親戚、友人などの「お墓参り」へ行く先々によっては宗派や慣習にちがいがあるかと思います。なので一般的な流れや作法を頭に入れておけばいいそうなんです。
- 「お墓参り」と聞くと…「かしこまったイメージ」や「きちんとしなきゃいけないイメージ」を持たれている方が多いかと思いますが、色々と調べた結果『ご先祖様や故人を思う、その気持ちが大切✨なので気軽にお墓参りへ出かけましょう〜』と書かれていることが大半でした。
『ご先祖さまや故人を思う、その気持ちが大切✨』ってとこにアコさんは心がポッと救われた気持ちになりました!というのは…
おじいちゃんやおばあちゃん、お父さんに今はもう会うことができないけれど…お墓の前で「”会いにきたよ、今年の夏はどうですか?!”」と小さい頃から毎年お墓の前で聞いていたこと、それは良いことなんだって思えたからです✨
来年も再来年もずっと、ず〜っと変わらずに続けていこうと思いました ( ^ω^ )
ここから先は「お墓参りの一般的なマナー」について調べたことをアコさんなりにわかりやすくお伝えしたいと思います。
※宗派によっては異なることがございます。
お墓参りへ行くのに
適している時期ってあるの?!
お墓参りには
『いつ行かなければならない』という
決まりはないそうです。
- 日常的にお墓参りをする人
- 年に1回や数年に1回お墓参りをする人
ここ最近では、進学や就職、結婚、出産、地元を離れる方も多くお墓のある場所と居住地が遠く離れることも珍しくはない世の中だそうです。
人生の節目のときにご先祖様や故人への近況報告を兼ねてお墓参りをすることも良いみたいです。
↓ココから先は「一般的なお墓参りを行うのに適した時期」を
調べてみましたので
気になる方は
参考にしてみてください
| お盆 | お墓参りに行く人がもっとも多い時期は「お盆」だそうです。 お盆には『ご先祖様や故人が家に帰ってくる』と言われているため、初日じゃなくても、お盆期間中であればいつでも行っていいそうなんです。 「7月盆→7/13〜7/16」「8月盆→8/13〜8/16」 地域で異ります |
| お彼岸 | 遠方に住んでいる人は、お盆とお彼岸にお墓参りをするのが一般的だそうです。 お彼岸とは「春」と「秋」の年2回あります。 3月の春彼岸は「春分の日を中日とした前後3日間を含む7日間」であり、9月の秋彼岸は「秋分の日を中日とした7日間」だそうです。 ーーーーーーーーー 春分の日と秋分の日は「昼と夜の長さが同じ」になります。 この世とあの世の距離が近くなるとも言われ、ご先祖様とも近くなるため「お墓参りをするのに適している」といわれてるそうです |
ーーーーーーーーーーーー
春分の日▶️その日を境に夏に向かって→1日の日照時間が長くなる
秋分の日▶️冬に向かっていくため→1日の日照時間が日に日に短くなっていく
| 命日 | 故人の命日には2種類あります。 ・「祥月命日(しょうつきめいにち)」▶️亡くなった月日>年に1回 ・「月命日」▶️亡くなった日>祥月命日を除いた年に11回 ーーーーーーーーー 一般的には『年に1回祥月命日にお墓参りをして、毎月の月命日にお参りに行く人もいる』そうです |
| 年末年始 | お墓参りを年末年始にする場合はご先祖様に、 年末には「1年の報告」年始には「新年の挨拶」ができます ーーーーーーーーー また、普段は遠方に住んでいる家族や親族の人たちは年末年始に帰省したり集まったときに「お墓参りをする」には適しているそうです。 ※年末年始の「霊園の開園時間が通常とは異なるケースがある」ため事前に調べてから行くようにした方が良いそうです |
お墓参り(供養)に
おこなうことってなに?!
仏教においては『五供(ごく)をお供えして合掌すること』が
供養の基本だそうです。
その『五供(ごく)』とは…『香』『花』『灯燭』
『浄水』『飲食』
| 香 | お線香の香りにより「心と身体が清められる」と言われているそうです |
| 花 | お参りをする人に向けて飾り「心穏やかにする意味」もあるそうです |
| 灯燭(とうしょく) | お線香に火をつけることで「煩悩を消し明るく照らす光の象徴を意味する」そうです。火を灯すこと自体がお供えになり、お墓の場合は石灯籠がその役割を果たしています |
| 浄水 | 清らかな水をお供えすることで「お参りをする人の心が洗われることを意味している」そうです。墓石の水鉢(墓石中央のくぼみがある部分)に新鮮なお水を張ります |
| 飲食 | 私たちが普段食べているものと同じものをお供えするといいそうです。 お墓には「故人の好物や季節の食べ物などを選び持っていかれると良い」みたいなんです。 お参りをした後は捨ててしまわずに、持って帰っていただくこで「ご先祖様や故人との繋がり」を表します |
『気持ちがこもっていれば、すべてが揃っていなくても構わない』そうです
『ご先祖様や故人へ対する気持ちが何よりも大切』ってことですよね!
「お墓参り」の
決められた手順ってあるの?!
※あくまで「一般的な手順」
であって、
「絶対にこうしなきゃいけない」ってこと
ではないそうなので
ご先祖様や故人へ対して
『心を込めておこなうこと』が
なによりも大切なこと
なんだと思います
| 1、手を洗って清める | お墓参りをする前に、まずは手を洗って清める |
| 2、お墓の掃除をする | 1▶️墓前で合掌してからはじめる 2▶️枯葉や雑草、くもの巣などをとってお墓まわりをキレイにする 3▶️墓石に水をかけながら雑巾で汚れを落とす |
| 3、手桶に水を汲んでくる | キレイな水を汲み柄杓で墓石に打ち水をして清める |
| 4、花立にお花を供える | 花立てにまだ花が残っていればキレイにしてから花を供える |
| 5、お供え物を供える | お菓子や果物などを置く |
| 6、お線香をあげる | お線香に火をつけ口で吹き消さず手で振るようにする |
| 7、拝礼(合掌)する | 複数人の場合は、お墓に眠る故人と近しい間柄の人から順番にお参りをする |
| 8、お参りが終わったら… | お供え物は持ち帰り自宅でいただくようにする(→そのままにしておくと墓石にシミやサビができたり、カラスが食べ散らかすことがあるため) |
「線香」は、そのまま燃やし切ります。
「お花」は、そのままにしておいて構いそうです。
以上が色々と調べた結果の
「一般的なお墓参りの手順(流れ)」だそうです
そして…お墓参りに行く際には「守るべきマナー」がいくつかあるそうなんです!
霊園(お墓)には、いろいろな方々が「お参りをしに来られる場所」でもあり、その一人一人にとって大切な空間(場所)でもあります。
自分以外のほかの方々に配慮しながらご先祖様や故人の供養をするよう心がけていきましょう✨
- 華美な服装にならないように心がけること
- お墓に供える花に少しだけ気をつかうこと
- 霊園にはルールがあること
- お墓参りの「お参り」には順番があること
一つ一つカンタンに説明をしていきます✨
| ①華美な服装はしない | お墓参りには「先祖に感謝や弔意を伝える」という目的があるそうです。 なので法要ではない場合、特に決まった服装はないみたいで喪服を着る必要もないですし普段着ている服装で構わないと言われています。 |
| ②お墓に供えるお花について | 菊が用いられることが一般的であり菊は「仏花(ぶっか)」と呼ばれる花で仏壇などに供える花としてふさわしいとされています。 バラのようにトゲのある花や香りが強い花に関してはお供えには不向きだと言われています。 必ずしも菊でなければいけないと言うわけではなく「故人が好きだったお花を供えること」も良しとされている。 |
| ③霊園のルールを守る | 霊園にはルールが定められています。 ペットを同伴してもいいかどうか、火の元の管理についてやお供え物の管理の仕方、開園時間などいくつかあるかと思います。 他のご家族に迷惑をかけないように霊園のルールをよく理解して守ることが大切。 |
| ④お墓参りの順番について | 親族などが集まってお墓参りに行く場合、誰からお参りをするのかという問題があります。 まずは全員揃ってお墓の前で合掌をして、その後は故人と関係が近い人から順番にお参りをしていくことが一般的だそうです。 |
親戚の家族と何年か前に「お墓参りが一緒の時間帯」になったことがあって「お参りをするとき」に”譲り合い”じゃないけど「どうぞ〜どうぞ〜」みたいな状況になったことがありました。
『ご先祖様や故人と関係が近い人から順番にお参りをしていくこと』は知らなかったことの1つだったので知ることができて…
ほんとよかったぁ〜
まとめ
今の今までずっと…お墓参りについての「流れや作法」を気にしたことがなかったので改めて調べてみると知らないことだらけだったので知ることができてアコさん自身、気づき✨がたくさんあって勉強になりました!
「お墓参りについて」はじめて調べてみました。
改めて”お墓参りの大切さ”や”供養する意味”を知ることができたので
来年からは父が眠っているお墓へ行った際にはすぐに掃除をはじめるんじゃなくて『家族で合掌してから』はじめていきたいと思いました✨
そして父には「いつも空から見守ってくれていてありがとう」と感謝の気持ち(心)を口に出して言いたいと思いました✨
「お墓参り」をすることで『ご先祖様や故人を供養する心の持ちよう』が少し変わりました。今いる「家族を大切にしよう」とか「生きているだけで幸せなことなんだった」とか…改めて実感しちゃいました。
日常をもっと丁寧に生きよう、父やおじいちゃん、おばあちゃんは亡くなっていてもう会えないけど、近くできっと「いつも見守ってくれている」し、何か予想もしなかったアクシデントが起こったとしても「助けてくれている」ような気がしています。
小さい頃は「お墓参りの意味」なんて分からなくても…
家族でお墓参りに行くこと、大人達の真摯な姿勢を小さいながらも生で見てきて感じ取ってきたことは『今でも記憶として心に残っているもの』なんですね。
お墓に行くたびに「怖さ」と「物静かな空間」が嫌すぎて、
朝から不機嫌になっていたことも…しばし…ありました(>_<)
ーーーーーーーーー
『お墓参り』は「日常忘れがちな感謝の気持ち(心)」や「人を想う気持ち(心)」を思い出させてくれる場所だとも思っています。
49歳の今、20代30代では感じられなかった〜あの独特な空間がなぜか今は心地がよくて「人が人を想う心静かな時間が実はとっても大切なことなんじゃないか」ってことに、この歳になって気づきはじめてきたところです✨
この「お墓参りの慣習」は次世代にも受け継いでいってほしい〜
日本の文化の1つでもありますし日本人に生まれてよかったとも思います!
なくならないでほしいなぁ〜こういう慣習って!!
あなたの貴重なお時間を使って最後まで読んでいただき
『ありがとうございました』 🙏
※下記にコメント欄があるので
あなたの人生の中で「心に残っている”お墓参り”のエピソード✨」を1つ
教えていただけたらアコさんの活力になります。













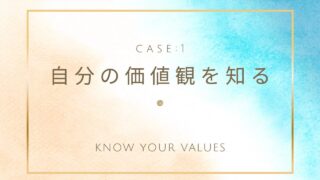
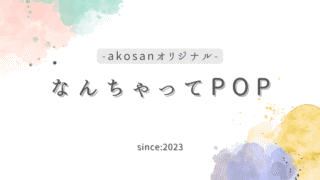





墓の前で供養した後に、お供物をその場で食べる』っていう行為珍しいかもしれませんがなんか亡くなったお父様と和気藹々と食べている光景が浮かんで微笑ましく感じました。
お父様も喜んでいると思います😊
みかりんさん
コメントをくださってありがとうございます。嬉しいです!
『お墓の前でお供物をいただく慣習』って、小さい頃から私の中では「当たり前になっていること」なので
人から「珍しい〜」とよく言われます。それでも、きっと私はこれからもず〜っと続けていく「お墓参りのかたち」なんだと思います。
お墓を見ながらお供物をいただいているとき毎年感じること。食材や果物、飲み物が「いつも以上になぜか、おいしく感じること✨」
亡くなった父だけじゃなく、ご近所さんのお墓の方々も「みんなでおいしくいただいた✨」感覚にもなります。
どうなんでしょうね、亡くなった父も一緒に食べてますかね?!一緒に食べててほしいなぁ〜ほんとに😀